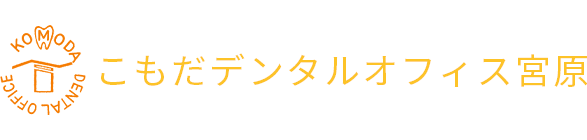子どもの乳歯の歯並びを見て、「隙間がないけど大丈夫?」と心配になったことはありませんか。乳歯の時期は、永久歯に生え変わるための準備期間でもあり、この段階での歯並びの状態が将来の歯並びや噛み合わせに影響することもあります。特に、乳歯の間に自然な隙間が見られない場合には、注意が必要なケースもあるのです。今回は、子どもの歯並びに隙間がない理由や、将来への影響、日常生活でできる工夫について解説します。
1. 子どもの歯並びに隙間がないとどうなる?
乳歯は本来、永久歯よりもサイズが小さく、成長に合わせて隙間があるのが自然な状態です。しかし、個人差によっては隙間が見られないこともあります。その理由は複数あり、成長過程や遺伝、生活習慣などが関係しているとされています。
①顎の発育の程度
成長過程で顎が十分に広がっていないと、乳歯が隙間なく並ぶことがあります。顎の幅が狭いままだと、将来の永久歯が生えるスペースが足りなくなる可能性があります。
②乳歯のサイズ
もともとの乳歯が平均よりも大きい場合、自然な隙間ができにくい傾向があります。これは遺伝的な要因も関係しており、両親の歯のサイズや顎の形を引き継ぐことがあります。
③口呼吸や舌の位置
普段から口呼吸をしていたり、舌が正しい位置にない(低位舌)場合、顎の成長に影響し、歯が並ぶスペースが狭くなることがあります。
④食事や咀嚼習慣
やわらかい食べ物ばかりを食べる習慣があると、顎の骨に十分な刺激が加わらず、発育が不十分になることがあります。現代の食生活も一因として考えられます。
⑤姿勢や癖の影響
うつぶせ寝や頬杖、指しゃぶりなどの癖は、顎や歯並びに影響を与える可能性があります。
⑥遺伝的要因
両親のどちらか、または両方の歯並びや顎の形が似ている場合、子どもも同様の傾向を持つことがあります。
隙間がないからといって必ずしも問題があるわけではありませんが、成長に伴い歯並びや噛み合わせに影響する可能性もあるため、注意深く見守ることが大切です。
2. 子どもの歯並びに隙間がない場合に考えられる将来の影響
乳歯に隙間がない状態が続くと、永久歯が正しく生えるスペースが足りなくなることがあります。これが将来の歯並びにどのような影響が出るか、具体的に見ていきましょう。
①永久歯が重なって生える可能性
スペース不足により、前歯や犬歯が重なって生えてくることがあります。いわゆる「歯のガタガタ(叢生)」の状態になることが多く見られます。
②噛み合わせのずれ
歯が本来とは異なる位置に生えると、上下の歯の噛み合わせが合わなくなることがあります。これにより、発音や咀嚼機能に支障が出る場合もあります。
③永久歯の生え変わりの異常
永久歯が適切な位置から生えられず、内側や外側からズレた場所に出てくることがあります。これにより歯列が乱れやすくなります。
④虫歯や歯周病のリスク
歯並びが乱れると、歯磨きがしにくくなり、磨き残しが増える傾向があります。その結果として、むし歯や歯ぐきのトラブルが発生しやすくなることがあります。
⑤将来的な矯正治療の必要性
歯並びが大きく乱れてしまうと、将来的に矯正治療を検討する必要が出てくることがあります。早めに対応することで、治療の選択肢を広げられる可能性があります。
⑥口元の見た目や発音への影響
歯並びや噛み合わせは見た目だけでなく、表情や発音にも関わります。サ行やタ行の発音がしにくくなるケースもあります。
このように、乳歯に隙間がない状態は、将来の口腔環境に影響する場合があるため、早めに気づいて適切に対応することが大切です。
3. 子どもの歯並びの隙間が気になるときにできる日常の工夫
乳歯の隙間が気になる場合でも、すぐに矯正が必要というわけではありません。まずは家庭でできることを取り入れ、必要に応じて歯医者に相談することが大切です。
①よく噛む食習慣を意識する
顎の発育を促すためには、しっかりと噛むことが大切です。硬すぎる食品は避けつつ、適度に噛み応えのある食材(根菜類や繊維質の野菜、少し硬めに炊いたごはんなど)を食事に取り入れましょう。
②正しい姿勢を保つ
うつぶせ寝や頬杖、猫背などの姿勢は、顎の発育や歯並びに影響することがあります。特に、食事中や読書・テレビを見るときの姿勢には注意し、頭をまっすぐに保つことを意識づけましょう。
③鼻呼吸を習慣づける
口呼吸が習慣化すると、舌の位置が下がり、顎の成長に影響する場合があります。日中に口が開いている、寝ているときにいびきをかく、朝起きたときに口が乾いているといった場合は、口呼吸の可能性があります。
④舌や口まわりの筋肉を鍛える遊び
風船をふくらませる、おしゃべりをたくさんする、ストローで飲むといった遊びや習慣は、口の筋肉や舌の動きを鍛えるのに役立ちます。これらの動作が、正しい舌の位置や唇の使い方を育てるのに役立ちます。
⑤仕上げ磨きで観察する
毎日の仕上げ磨きの際に、歯並びの変化や隙間の有無を確認しておくと、異常に早く気づけることがあります。前歯の向きが変わってきた、永久歯の生える方向がずれているといったサインを見逃さないようにしましょう。
これらの工夫は、すぐに結果が出るものではありませんが、日々の積み重ねが将来の歯並びに影響を与える可能性があります。
4. 新居浜市宮原町の歯医者 こもだデンタルオフィス宮原の小児矯正
愛媛県新居浜市、バス停「喜光地」より徒歩3分の歯医者こもだデンタルオフィス宮原では、「子どものむし歯ゼロ・大人の歯周病ゼロ」を理念に掲げ、予防中心の歯科医療を提供しています。
13年以上の臨床経験を持つ院長が、一人ひとりに寄り添った丁寧な診療を行い、特に小児歯科と小児矯正に注力しています。
令和7年7月に医院を移転し、大人と子どもの診療スペースを分離。新居浜市では唯一(※1)の、小児歯科専用、お子さんがリラックスできる、アニメ視聴モニター付きの天井モニターや広々としたキッズスペースを備えた「こども専用診療室」を整備しました。
※2025年7月時点
こもだデンタルオフィス宮原では0歳から始める健診や口腔育成に加え、子どもの歯並びや呼吸機能の予防・矯正として次の診療メニューに対応し、お子さんの健やかな発育と歯並びをサポートしています。
➀小児睡眠時育脳サポート装置『Vkids(vキッズ)』(3歳から5歳のお子様へ)
睡眠時に装置を装着することにより、お口を広くし、顎と舌を子どもたちが自然に前方へ持っていくように促すことで呼吸をしやすくなります。 歯がある程度生えそろい始める3歳頃から使用でき、早めにお口を広くし、下の位置を正常にサポートすることにより予防矯正の役割も担うとされています。
➁床拡大矯正『バイオブロック』(5歳以上のお子様へ)
日本人の顎は比較的狭く歯が十分に整列するスペースが不足している傾向があり、歯並びや嚙み合わせが乱れ全身の健康への影響を及ぼす場合があります。 子どものうちからできる対策である床拡大矯正『バイオブロック』は上顎を拡大するための取り外し可能な装置です。舌と歯のスペースを確保することを目的としています。
子どものうちから、予防矯正・小児矯正を行うことで将来のお子様の口腔環境を守ることを目指しています。
「食が細い…」「将来の歯並びが心配…」といったお悩みのご相談だけでも構いません。
少しでも気になることがあれば、愛媛県新居浜市で0才から通える歯医者 こもだデンタルオフィス宮原にご相談ください。
\\\新居浜市の歯医者 こもだデンタルオフィス宮原の小児矯正詳細はこちら///
まとめ
子どもの乳歯に隙間がない状態は、一見きれいに見えても、将来的に永久歯が並ぶスペースが不足し、歯並びや噛み合わせに影響することがあります。日常生活の中での食習慣や姿勢、呼吸方法などを意識しつつ、気になることがあれば歯医者に相談してみましょう。早めに気づき、対応することで、将来の口腔環境を守ることにつながります。子どもの歯並びに関してお悩みの方は新居浜市宮原町の歯医者「こもだデンタルオフィス宮原」までお問い合わせください。
監修:こもだデンタルオフィス宮原 院長:薦田 祥博(こもだ よしひろ)
経歴
・日本大学松戸歯学部 卒業
・デンマーク オーフス大学歯学部 短期研究生
・日本大学大学院松戸歯学研究科 卒業
・日本大学松戸歯学部 クラウンブリッジ補綴学講座兼任講師