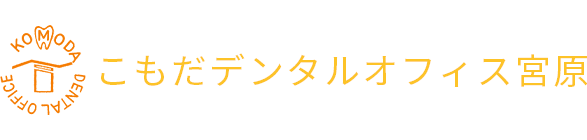子どもの歯並びに違和感を覚え、「うちの子、矯正は必要なのかな?」「いつから始めるべきなんだろう?」と悩んでいる親御さんもいるのではないでしょうか。小児矯正は、歯の生え変わりや顎の成長に合わせて進める必要があり、開始のタイミングを見極めることがとても重要です。しかし、適切な時期や判断の基準を知らずに矯正のタイミングを逃してしまうと、将来の歯並びや噛み合わせに影響が出る可能性があります。そこで今回は、小児矯正の開始時期と判断する基準について解説します。
1. 子どもの矯正はいつから?小児矯正の開始時期
小児矯正には、子どもの成長過程に応じた2つの治療段階があり、それぞれ開始時期と目的が異なります。開始の適切なタイミングを知ることで、効率的な治療が行える可能性が高まります。
<第1期治療>6〜10歳ごろ
乳歯と永久歯が混在している「混合歯列期」に行う矯正で、主に顎のバランスを整えることが目的です。この時期の矯正は、永久歯がきれいに並ぶためのスペースを確保したり、顎の成長を正しい方向に導いたりすることに重点を置きます。歯そのものを大きく動かすのではなく、成長を利用した予防的な矯正で土台作りの時期です。
<第2期治療>12歳以降
永久歯がすべて生えそろった後に行う矯正で、主に歯並びや噛み合わせを整える治療です。成人の矯正とほぼ同じ内容になりますが、成長期で骨の柔軟性があるため、治療が進めやすい時期とされています。
このように、小児矯正は子どもの成長段階に応じて適切な時期があります。歯並びや噛み合わせに違和感があると感じたら、乳歯と永久歯が生え変わる小学校入学前後を目安に一度、歯医者で相談することが大切です。
2. 小児矯正を検討すべき特徴とは
小児矯正は、見た目の歯並びを整えるだけでなく、顎の発達や噛み合わせ、発音、呼吸など、機能的な面で全身の健康にも大きく関わります。以下のような変化が見られる場合は、小児矯正の検討をおすすめします。
①前歯の歯並びがガタガタしている
永久歯が生え始めた頃に、前歯が重なっていたり、ねじれていたりする場合は、将来的な歯列不正の可能性があります。成長によって自然に治ることもありますが、顎のスペースが足りていない場合は歯が生える場所が無いため、矯正が検討されるケースもあります。
②上顎または下顎が大きく出ている、あるいは引っ込んでいる
いわゆる「出っ歯」や「受け口(反対咬合)」といった状態は、見た目の問題だけでなく、発音や咀嚼などの機能面にも影響します。受け口は成長によって目立ちやすくなるケースもあるため、気になる場合は、早めに歯科医師に相談してみてもよいでしょう。
③口呼吸やいびきがある
鼻ではなく口で呼吸する「口呼吸」は、顎の発育に悪影響を及ぼし、歯並びや顔つきの発育にも関わることがあるため、注意が必要です。睡眠時のいびきがある場合も、顎の成長に問題がある可能性があるため、一度専門的なチェックを受けましょう。
④噛み合わせが上下でずれている
上下の前歯が噛み合わない「開咬(かいこう)」や、横にずれている「交叉咬合(こうさこうごう)」なども、子どもの成長期に矯正治療を検討することがあります。放置した場合、咀嚼機能や発音への影響が生じるケースもあるため、注意が必要です。
⑤いつも口を開けている、口が閉じにくい
口が常に開いている状態は、舌や口の筋肉が正しく使えていないサインで、顎や顔の成長に影響します。こうした癖は歯並びの不正にも影響する可能性があります。
このような特徴が見られる場合は、小児矯正を検討する一つの判断材料となります。気になる点があれば、早めに歯科医師に相談しましょう。
3. 小児矯正を始める前に知っておきたいこと
小児矯正は子どもの将来の健康や見た目に大きな影響を与える治療である一方で、「始めるにあたって何を知っておけばいいのか」が気になるのではないでしょうか。次に治療前に知っておきたい重要なポイントを整理しておきましょう。
①矯正治療は長期的な通院が必要
小児矯正は一度始めると、定期的な通院が必要になります。特に第1期治療では、成長の進み具合に合わせて装置を調整するため、月1回程度の来院が一般的です。また、治療期間は半年〜数年に及ぶこともあり、その期間に通院できるか検討する必要があります。
②必ずしも矯正が必要とは限らない
見た目に歯並びの乱れがあっても、成長とともに自然に改善するケースもあります。歯科医師による診断を受けた上で「今は経過観察でよい」「第2期治療のみで対応可能」などの判断がなされる場合もあるため、まずは歯科医師の意見を聞くことが大切です。
③矯正装置に慣れるまで時間がかかることもある
マウスピースや固定式の装置など、矯正方法によって装着感は異なりますが、初めての装置に戸惑う子どもも少なくありません。徐々に慣れていきますが、特に話しづらさや違和感を感じる場合は、無理に進めるのではなく、少しずつ慣らしていくとよいでしょう。
④家庭での協力が必要になる
矯正の効果を引き出すためには、日常生活での口腔ケアや装置の取り扱い、食事の工夫など、家庭でのサポートが重要です。特にマウスピース矯正の場合、決められた時間しっかり装着することが求められるため、保護者の方の声かけや見守りが大切になります。
⑤学校や習い事との両立を考慮する
装置によっては発音や表情に影響を与える場合もあります。子ども自身が通院や装置に対して抵抗感を持たないよう、説明や準備を丁寧に行い、学校生活や習い事との両立がしやすいタイミングを見計らってスタートすることが望ましいでしょう。
小児矯正をスムーズに進めるためには、子どもと保護者の方が一緒に理解を深め、納得した上で治療に取り組むことが大切です。
4. 新居浜市宮原町の歯医者 こもだデンタルオフィス宮原の小児矯正
愛媛県新居浜市、バス停「喜光地」より徒歩3分の歯医者こもだデンタルオフィス宮原では、「子どものむし歯ゼロ・大人の歯周病ゼロ」を理念に掲げ、予防中心の歯科医療を提供しています。
13年以上の臨床経験を持つ院長が、一人ひとりに寄り添った丁寧な診療を行い、特に小児歯科と小児矯正に注力しています。令和7年7月に医院を移転し、大人と子どもの診療スペースを分離。新居浜市では唯一(※1)の、小児歯科専用、お子さんがリラックスできる、アニメ視聴モニター付きの天井モニターや広々としたキッズスペースを備えた「こども専用診療室」を整備しました。※2025年7月時点
こもだデンタルオフィス宮原では0歳から始める健診や口腔育成に加え、子どもの歯並びや呼吸機能の予防・矯正として次の診療メニューに対応し、お子さんの健やかな発育と歯並びをサポートしています。
➀小児睡眠時育脳サポート装置『Vkids(vキッズ)』(3歳から5歳のお子様へ)
睡眠時に装置を装着することにより、お口を広くし、顎と舌を子どもたちが自然に前方へ持っていくように促すことで呼吸をしやすくなります。
歯がある程度生えそろい始める3歳頃から使用でき、早めにお口を広くし、下の位置を正常にサポートすることにより予防矯正の役割も担うとされています。
➁床拡大矯正『バイオブロック』(6歳以上のお子様へ)
日本人の顎は比較的狭く歯が十分に整列するスペースが不足している傾向があり、歯並びや嚙み合わせが乱れ全身の健康への影響を及ぼす場合があります。
子どものうちからできる対策である床拡大矯正『バイオブロック』は上顎を拡大するための取り外し可能な装置です。舌と歯のスペースを確保することを目的としています。
子どものうちから、予防矯正・小児矯正を行うことで将来のお子様の口腔環境を守ることを目指しています。
「食が細い…」「将来の歯並びが心配…」といったお悩みのご相談だけでも構いません。
少しでも気になることがあれば、愛媛県新居浜市で0才から通える歯医者 こもだデンタルオフィス宮原にご相談ください。
\\\新居浜市の歯医者 こもだデンタルオフィス宮原の小児矯正詳細はこちら///
まとめ
子どもの矯正は、開始時期や治療方法の判断が将来の歯並びや噛み合わせだけでなく、全身の健康にも関わる大切な治療です。特に第1期治療は、成長を活かせる貴重なタイミングといえます。ただし、すべての子どもに治療が必要なわけではなく、経過観察が適している場合もあります。保護者が一人で判断せず、歯科医師と相談しながらを治療計画を立てることが求められます。
新居浜市、宮原町周辺で「子どもの矯正はいつから?」とお悩みの方は、こもだデンタルオフィス宮原へご相談ください。
監修:こもだデンタルオフィス宮原 院長:薦田 祥博(こもだ よしひろ)
経歴 学会・所属
・日本大学松戸歯学部 卒業
・デンマーク オーフス大学歯学部 短期研究生
・日本大学大学院松戸歯学研究科 卒業
・日本大学松戸歯学部 クラウンブリッジ補綴学講座兼任講師
・日本補綴歯科学会
・日本老年歯科学会
・日本顎関節学会
・IADR(国際歯科研究学会)